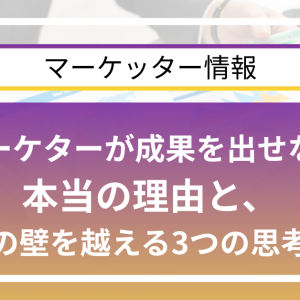TikTokにおける「会話型ストーリーテリング」の台頭:セリフで魅せる動画設計とは?
TikTokの動画表現が、今また一つ進化を遂げつつあります。
注目されているのは、セリフを軸とした「会話型ストーリーテリング」の台頭です。
「セリフで魅せる」動画フォーマットとは、一人芝居のような形で登場人物のセリフだけで物語が進行する構成や、チャット風のやり取りを模した脚本スタイルのことを指します。
Z世代・α世代のユーザーにとって「長いナレーションはしんどい、でも心は動かされたい」という矛盾を解消する手法として、急速に支持を集めています。
この記事では、TikTok上で実際に流行している会話型動画の演出スタイルや、なぜ今この形式が支持されているのか、さらにブランドや企業が活用するための実践ノウハウまでを解説していきます。
なぜ「セリフ動画」が今、TikTokで刺さっているのか?
セリフを主体としたストーリーテリングがTikTokで急速に広がっている背景には、いくつかの明確な理由があります。
1. 情報疲れしたユーザーに「物語」を届けられる
TikTokユーザー、特にZ世代は毎日膨大な情報にさらされています。
その中で「説明的な動画」や「テンプレ的な紹介動画」には次第に飽きが生じてきました。
一方、セリフ中心の動画は、ストーリーを“体験”させることができます。
誰かのセリフとして提示されることで、視聴者は「客観的に観る→自分に置き換える」という没入プロセスを自然に辿るようになります。
2. ナレーションよりも「自分の声」として入りやすい
セリフは、語りではなく「人のやりとり」の形式をとるため、
「このやりとり、まさに自分も思ったことある」「このセリフ、自分が言いたかったことだ」と、
よりパーソナルな共感を生み出しやすくなります。
また、ナレーションでは感情移入しづらい層にも「セリフ=感情の断片」が届きやすいというメリットがあります。
3. 自然な演出で「AI臭さ」を払拭できる
近年のAIナレーションや生成アバターを活用した動画は急増していますが、「いかにも機械的な声」や「リアルすぎて逆に不自然なキャラ」に違和感を覚えるユーザーも増えています。
セリフ動画は、これを自然に包み込む手法の一つです。
生成ナレーションでも、セリフ形式にすることで「一人語りの違和感」を抑えることができ、ユーザーの受け入れハードルが下がります。
TikTokで見かける会話型ストーリーテリングの代表フォーマット
では、実際にTikTokで多く見かける会話型の動画フォーマットにはどのようなものがあるのでしょうか?代表的なスタイルをいくつか紹介します。
1. 一人二役構成(画角・声・字幕を切り替える)
同一人物が「AとB」など2役を演じ分けるスタイルです。
-
カメラアングルや服装を左右で変える
-
声を高低で演じ分ける
-
字幕色をキャラ別に変える
これにより、短時間で物語性を出すことができ、視聴者が「登場人物の関係性」に没入しやすくなります。
特に恋愛系・日常会話系・自己対話(「本音 vs 建前」)などに活用されており、再現性の高さからUGC化されやすい特徴も持ちます。
2. チャット形式(吹き出し・LINE風UI)
LINE風やSNS風のチャット画面を模したスタイルも人気です。
-
セリフがテキストチャットのように表示される
-
効果音や既読演出を加える
-
感情の高まりを打ち込み速度で表現する
文字の流れが視聴者の“読解速度”に合っており、視聴完了率が高くなる傾向があります。特にドラマ・推理・告白系の演出に強いです。
3. 心の声だけで構成された「内省系モノローグ」
セリフとはいえ、実際には「登場人物の心の声」で展開される形式です。
-
あるシーンに対して心のつぶやきが挿入される
-
主観視点+心の声で没入感を演出
-
例えば「告白前の10秒間」「退職願を出す直前」など、感情の高まりに特化
このフォーマットは、Z世代の自己表現スタイルと相性がよく、「代弁してくれてありがとう」「自分の気持ちに言葉を与えてくれた」といった反応が得られやすいのが特徴です。
なぜマーケティングでも「セリフ設計」が重要になるのか?
ここまで見てきたように、TikTokのユーザーが求めるのは「説明」ではなく「物語を感じること」です。
セリフ中心の演出は、企業やブランドにとっても次のような効果をもたらします。
1. 視聴者の“感情導線”を誘導できる
ナレーションではなくセリフを用いることで、感情の起伏や展開を細やかに設計でき、
視聴者に「自然に共感してもらう」導線を作りやすくなります。
特に、
-
BtoC領域での購買心理
-
採用系での社員目線訴求
-
トラブル事例→解決提案までのドラマ展開
などにおいて、セリフ構成は効果的です。
2. ナレーションやCGアバターの補完手段になる
生成AIによる動画制作では、「セリフ構成」を取り入れることで、演出の“人間味”を補うことができます。
たとえば、生成されたナレーションを1文ごとにセリフ調に分割し、字幕も会話風にすることで、
「これはナレーションです」感を払拭し、視聴者の違和感を軽減します。
3. スクリプト設計のベースが体系化しやすい
会話形式のスクリプトはテンプレート化がしやすいため、運用体制でも制作効率を高めやすい利点があります。
-
商品を知らないAと知っているBの対話
-
購入を迷っている顧客と店員の対話
-
初めての人でも分かるようBがかみ砕いて説明する構成
このような形式は、プロットの汎用化にもつながり、制作チームの引き継ぎにも適しています。
TikTokマーケティングにおける「セリフ設計」実践のヒント
では実際に、企業アカウントがセリフ型ストーリーテリングを活用するには、どのようなポイントを押さえるべきなのでしょうか?
ヒント1:脚本を「やりとりベース」で書く
通常の構成案ではなく、「A:〇〇」「B:〇〇」という形式で最初からスクリプトを設計します。
視聴者に“会話を盗み聞きしているような感覚”を与えることがポイントです。
ヒント2:キャラ設定を明確にする
登場する人物(仮想でもよい)の性格・立場・口調を決めておくことで、セリフにブレがなくなります。
-
例:元気な若手社員×冷静なベテラン
-
例:悩める顧客×商品に詳しい友人
こうした「キャラの化学反応」で、セリフのリアリティがぐっと高まります。
ヒント3:言葉の余白を活かす
すべてを説明しすぎず、視聴者の想像力を刺激する言葉の「間」や「含み」を意識することで、
“考えさせる動画”として保存やコメントが促進されます。
まとめ:セリフは、TikTokにおける「共感スイッチ」になる
TikTokのコンテンツは、次第に「映像」から「体験」へと進化しています。
その中で、セリフを使った会話型ストーリーテリングは、ユーザーの心を動かす「共感のスイッチ」として機能しています。
ブランドが伝えたいことを、ナレーションやテロップで説明する時代は終わりつつあります。
これからは、「セリフという形で感情を伝える」ことが、エンゲージメントの鍵になるのです。
次に作るTikTok動画は、ぜひ一行のセリフから始めてみてください。
その言葉が、誰かの心を動かす第一歩になるかもしれません。