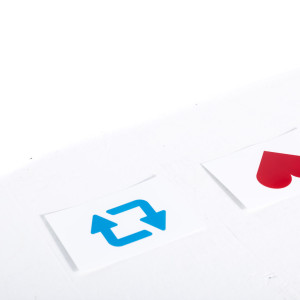TikTokで「感情」を設計する時代へ:ナラティブ×共感ベースのブランド演出戦略とは?
TikTokにおける動画制作は、もはや“面白いかどうか”ではありません。
2025年春の現在、Z世代・α世代に本当に届く動画とは、「感情が動く構成」がなされている動画です。
企業アカウントにおいてもこの傾向は顕著で、注目されているのが「感情設計」や「ナラティブ設計」と呼ばれる手法です。
短尺動画の中で、いかに共感を引き出し、心を動かす体験を演出できるかが、バズよりも“信頼”や“購買行動”に直結する時代となっています。
本記事では、TikTokにおける最新の「エモーショナル・デザイン」手法とその背景、ブランド活用のポイント、そして成果を出している事例までを徹底的に掘り下げていきます。
感情設計とは?TikTokで注目される「感情の流れを演出する動画構成」
「感情設計(Emotional Design)」とは、視聴者が動画を通して感情的に反応するように、意図的にストーリーや演出を構成する手法のことです。
TikTokにおける感情設計では、次のようなポイントが重視されます。
-
共感:「わかる」「自分もそうだった」と思わせる導入
-
没入:視聴者が“自分ごと化”できる感情の流れ
-
感動・驚き:予想外の展開や心に残るメッセージ
-
行動喚起:保存・コメント・共有・購入などへの自然な誘導
感情を軸にした動画は、アルゴリズムの観点でも評価されやすく、視聴完了率や保存率の向上につながるため、マーケティング戦略としての重要性も年々高まっています。
2025年春の最新トレンド:感情に訴えるナラティブ構成が人気
最新のTikTokトレンドを分析すると、以下のような「ナラティブ構成+感情訴求型」の投稿がバズの主流になっています。
1. ナレーション×字幕の没入型ストーリーテリング
ナレーションを活用し、自分の体験や感情を語る構成がZ世代に刺さっています。特に効果的なのは以下の演出です。
-
感情トーンをコントロールできるAIナレーション
-
タイピング音+1行ずつ表示される字幕
-
「〇〇だった日の話」「これは、私が変わった瞬間」といった導入
ナレーションを通じて“語り手の存在”を感じさせながらも、視聴者が自分を重ねられる余白を残すことで、共感が生まれやすくなります。
2. コメントと連動する「感情リレー」動画
視聴者コメントをもとに次の動画を構成する「感情リレー型投稿」も急増中です。
-
第1話:「こんなことがあった」→ コメントで感想や体験が集まる
-
第2話:「コメントで“わかる”ってくれた人へ」→ 共感の声を拾って続編を制作
このような投稿は「ユーザーとの対話」から成り立っており、ブランドアカウントでも取り入れやすい構成です。
3. ナラティブに基づくCTA最適化
「動画の最後に何を言うか」は、エンゲージメントを大きく左右します。
-
「この気持ち、わかる人だけ保存して」
-
「誰かに届く気がしたら、共有してみて」
-
「“わかる”って思ったら、コメント欄で教えて」
感情的な流れを止めずにCTAを自然に挿入することが、押し付けがましくない行動喚起に繋がっています。
ブランドがTikTokで感情設計を活用するための戦略
企業アカウントが感情設計を取り入れる際は、次の3つの視点からアプローチすることが重要です。
1. 「人」を主役にする:ブランドではなく“語り手”を設計
TikTokでは、商品やサービスの紹介だけではユーザーの心は動きません。
そこで注目されているのが、「中の人」「お客様の声」「開発者の想い」などをナラティブとして構成する方法です。
例:
「この開発には、5年分の“悔しさ”が詰まっています。」
「一人のユーザーの声が、すべてのきっかけでした。」
こうしたストーリーは、“企業のストーリー”というよりも、“人間のストーリー”として共感を呼びます。
2. スクリプト設計を取り入れ、動画構成に起承転結を
感情を動かすには、構成が鍵です。
-
起:導入で共感や問いを提示
-
承:背景や経緯を簡潔に展開
-
転:心が揺れる変化や決断
-
結:気づきや呼びかけ、余韻
このフレームを使ってスクリプトを事前に設計し、ナレーションや字幕に落とし込むことで、視聴者の離脱を防ぎ、記憶に残る投稿に仕上がります。
3. データと感情のハイブリッドでPDCAを回す
TikTokの分析ツールやAI動画補助機能では、保存率・完了率・コメント率などの「感情反応に近い指標」が確認できます。
これらをもとに、
-
どの構成が心に残ったのか?
-
どの言葉が刺さったのか?
-
どの動画が保存されたのか?
を振り返りながら、スクリプトと構成を微調整していくことで、感情設計はより洗練されていきます。
実際に成果を出しているブランドの取り組み
ここでは、感情設計を取り入れて成果を上げている実際のブランド事例を紹介します。
海外コスメブランドA社
-
商品紹介よりも「開発者の葛藤ストーリー」を前面に
-
ナレーションと字幕による感情表現が大きな反響を呼ぶ
-
視聴完了率が平均の1.8倍、コメント数も3倍以上に
日本の中小メーカーB社
-
地方の職人を紹介するドキュメント風構成
-
「声を出さない」字幕中心の構成が没入感を生み、フォロワーが急増
-
保存数が10倍近く伸びた動画も登場
→ 大企業よりも「リアルな物語」が映える中小ブランドとの相性が良いのも特徴です。
まとめ:TikTokは“情報”より“感情”で動かす時代に突入した
TikTokにおけるマーケティングの本質は、「認知」でも「バズ」でもありません。
いま求められているのは、「共感」や「理解」、そして「感情の共有」です。
-
ナレーションで語りかける
-
字幕で言葉をかみしめさせる
-
コメント欄で物語を続けてもらう
これらすべてが、“感情を軸に設計されたブランド体験”の一部です。
次に投稿する動画は、ぜひ「感情から逆算してスクリプトを設計する」スタイルで試してみてください。
それは、“誰かの心に残るブランド”への第一歩になるかもしれません。