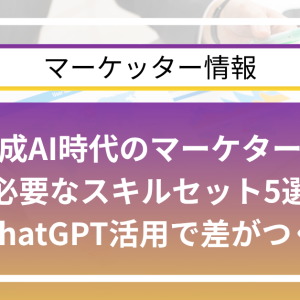「AI声変換フィルター」トレンドの急拡大:Z世代がハマる“なりきり型ナレーション動画”の魅力とは?
2025年春、TikTok上で急速に広がっているのが「AI声変換フィルター(AI Voice Filter)」を活用した動画です。
これは、撮影者の実際の声をAIで加工・変換し、別人のようなナレーションやボイスで動画を構成する演出手法。
声を変えることでキャラクター性やストーリー性を持たせることができ、Z世代・α世代を中心に“なりきり系コンテンツ”として人気を集めています。
特にTikTok内では、以下のような傾向が見られます。
-
「子ども風」「おばあちゃん風」など、年齢を超えたなりきり演出
-
キャラクターを作って物語を語る“ボイス・ストーリーテリング”
-
動画を自分で作るのではなく“別の人格で語らせる”自己表現手法
本記事では、このAI声変換フィルターを使ったトレンドの特徴と拡大理由、活用ジャンル、企業のマーケティング活用可能性までを詳細に解説します。
AI声変換フィルターとは?TikTokにおける最新機能の概要
TikTokやCapCut、または一部の外部ツール(例:Voicemodなど)と連携し、撮影時または編集時に声質を自由に変換できるフィルター・エフェクトが登場しています。
主なフィルター例:
-
キッズボイス(5歳児のような声)
-
老人ボイス(70代女性風)
-
アニメ声(高音・チューニング調)
-
ロボ声(機械的な抑揚をもつ)
-
有名人風(本人ではないが似せた声質)
これらのフィルターは、投稿動画にユーモアや“演技性”を付加し、投稿者自身が物語の登場人物になりきる演出を可能にします。
なぜZ世代に「声の変換」が刺さるのか?背景にある4つの理由
このトレンドがZ世代やα世代を中心に急拡大している理由は、単なる“面白さ”だけではありません。
1. 自分を出しすぎたくない心理と自己表現の両立
「顔出しはしたくないけど、伝えたいことはある」
「本音を語りたいけど、自分の声だと恥ずかしい」
こうした感覚に応えるのが、“声の仮面”としてのAI変換です。
匿名性を保ちながら、オリジナルな世界観を演出できるため、自己表現の新たなスタイルとして受け入れられています。
2. なりきり・ロールプレイ文化との親和性
TikTokには、すでに以下のような“演技系”文化が根付いています。
-
台詞に合わせて演じる「リップシンク」
-
2人の人格を演じ分けるストーリー構成
-
キャラに成りきる「創作ナレーションシリーズ」
そこに“声の変換”が加わることで、さらに演じる自由度が拡張され、「素人×即興×演技」が融合したクリエイティブ空間が生まれています。
3. 音声コンテンツ消費との親和性
Z世代はYouTubeのナレーション動画やポッドキャスト、音声学習アプリなどを日常的に利用しており、“声のコンテンツ”への親和性が高い世代でもあります。
AI声変換フィルターは、その延長線上で自然に受け入れられていると考えられます。
4. 共感+笑いのバランスが取りやすい
声を変えることで、「ちょっと面白く」「ちょっと切なく」語れる構成が可能になります。
とくにTikTokでは「エモ×ユーモア」のバランスがウケやすく、加工された声が感情の振れ幅を演出しやすいというメリットがあります。
人気を集めているAIボイス活用動画のフォーマット
以下は、現在TikTokで人気を集めている「AIボイス×ストーリーテリング」形式の代表的な例です。
1. 子どもの声で語る「昔の自分」系
動画例:「7歳の私が、今の私に伝えたいこと」
→ 子ども風ボイスでナレーション。回想録や自己肯定感系動画として共感されやすい。
2. おばあちゃんの声で語る「人生アドバイス」系
動画例:「今日はあなたに一言だけ伝えたいの」
→ 優しい語り口調にすることで、言葉の重みと癒し感が生まれる。保存率・コメント率が高い。
3. 有名人風ボイスで「ツッコミ解説」系
動画例:「今の行動、芸能人Xだったら絶対こう言う」
→ 人気キャラや著名人風の声でナレーションすることで、パロディ要素が強調され、笑いとシェアを誘発。
4. アニメ風ボイスで創作ナレーション系
動画例:「これは、とある高校生が迎えた“卒業の日”の話」
→ 短編小説のようなストーリーをアニメ声で演出。シリーズ化されることも多い。
マーケティング活用への応用:ブランドがAI声変換を取り入れるには?
このトレンドは、個人クリエイターだけでなくブランドや企業にも応用の余地があります。以下は代表的なアプローチです。
1. 商品紹介を“キャラクターの声”で演出
例:「あなたの肌、最近こんな風に思ってるらしいよ(スキンケア商品紹介)」
→ 声の加工によって、商品が自分に語りかけるような構成に。TikTokならではの“軽さと没入感”を両立。
2. ブランドの世界観を声で構築
例:「このお店の物語を、おばあちゃんが語ります」
→ 企業や店舗のストーリーに情緒を持たせて語ることで、単なる紹介動画ではない“心に残る導線”に。
3. ユーザー参加型“声で遊ぶ”キャンペーン
-
「あなたの“過去の自分”を語らせよう」
-
「このテンプレで“ツッコミ動画”を作ってください」
→ 音声テンプレートを用意し、視聴者が自由に演出する「声UGC」を設計することで、拡散性とエンゲージメントの両立が可能です。
今後の展望:TikTokは「声で遊ぶSNS」へ進化するのか?
AI声変換フィルターの普及は、TikTokを単なる動画SNSではなく“ボイスエンタメプラットフォーム”へと進化させつつあります。
以下のような展開が今後予測されます。
-
ナレーションAIとのリアルタイム連携(キャプション自動→声変換)
-
複数キャラによる“音声ドラマ動画”フォーマットの確立
-
パーソナライズされたボイス演出(ユーザー属性ごとの声を選べる)
-
広告配信時に「声」まで自動生成されるダイナミック音声広告
TikTokは「映像を見せる」だけでなく、「声で感じさせる」メディアとしての役割を強めていく可能性が高まっています。
まとめ:「声が変わる」ことで動画は“人格”を持ち始めた
TikTokにおけるAI声変換フィルターのトレンドは、単なるエフェクトではありません。
それは、表現者が“キャラクター”として世界を語る手段であり、匿名性と没入性を両立するクリエイティブツールです。
これからのTikTok運用において、次のような問いを持つことが重要になります。
-
この動画を「誰の声」で語らせると、より刺さるのか?
-
本音を語るとき、“素の声”よりも“誰かになりきる”方が届くのでは?
-
自社のブランドは、「どんな声色で」ユーザーに語るべきか?
映像に続き、「声」もまた、表現設計の主軸になる時代がやってきています。
TikTokは今、声で感情を操作し、記憶に残すコンテンツの実験場として、さらなる進化を続けています。
今このトレンドをどう活かすかが、次のバズを生む鍵となるでしょう。