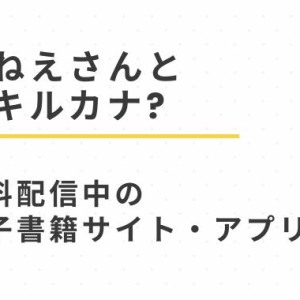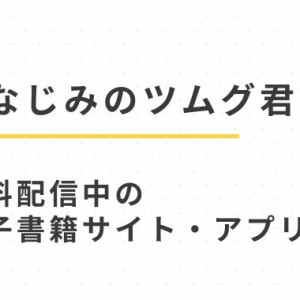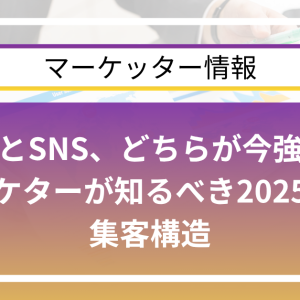TikTokで注目の「インタビュー風動画」演出とは?共感と語りで惹きつける新しいブランディング手法
TikTokにおいて今、インタビュー風の構成や語り口で作られた動画――いわゆる「共感インタビュー型動画」が急増しています。
「最近、こんなことがあったんですよ」
「これは、ある女の子の話」
「本当は誰にも言えなかったけど…」
こうした“誰かの語り”がナレーションやテロップで展開される動画は、エンタメ性よりも“感情の共有”に重点が置かれ、Z世代・α世代を中心に強く支持されています。
本記事では、このインタビュー演出型コンテンツがなぜ今TikTokで流行しているのか、どのような構成が支持されているのか、そして企業や個人がそれをどうマーケティングに活かすかを実践的に解説していきます。
「共感語り」フォーマットが増加している背景
TikTokにおけるこの新たな動画スタイルが拡大している理由は、以下の3点に集約されます。
-
顔出し不要でも感情を共有できる
ナレーションや字幕だけで物語を展開できるため、出演者の“素”を出さずにリアルな印象を与えられる。 -
視聴者が“第三者の視点”で安心して没入できる
自分が直接感情をさらすのではなく、他人の話として消化できるため、共感と没入を同時に得やすい。 -
“話を聞く文化”の再燃
ポッドキャスト、オーディオブック、YouTubeのインタビュー系コンテンツが広がる中で、「聞くことでつながる」文化がTikTokにも浸透してきている。
特に2025年は、「誰かのストーリーを聞いて自分と重ねる」という共感型視聴がTikTok上でも主流となりつつあります。
人気を集める「インタビュー風」動画の代表的な形式
では、具体的にどのような演出が視聴者に支持されているのでしょうか。以下に代表的なパターンを紹介します。
1. 架空人物の語り口で展開されるストーリー構成
例:「これは、大学を辞めたばかりの女の子の話」
→ ナレーション+字幕で構成され、登場人物が視聴者に語りかけるように感情を伝える。共感コメントが集まりやすく、「続きが見たい」シリーズ化も容易。
2. ノンフィクション風の“あるある再現”動画
例:「最近よくある相談内容って何ですか?」
→ 架空の“インタビュアー”と“語り手”の会話を再現。ユーザーは「それ、私のこと」と感情移入し、拡散されやすい。
3. ナレーションのみで展開される1人語り型
例:「昨日、道で泣いてる子を見た」
→ 登場人物は出てこず、風景映像+字幕+ナレーションだけで構成される。テンポやBGMが情緒を作り、保存数が伸びやすい。
4. “あなたへ語りかける系”エモ演出
例:「誰かに言われたことがずっと気になってる、そんなあなたへ」
→ ユーザーの“心の内”に語りかけるような構成で、ナレーションや字幕が直接感情に訴える。
このような動画は、視聴者との距離感を近づけ、「個人対個人」の関係を疑似的に演出することができます。
共感インタビュー動画が生む効果とは?
このフォーマットがTikTok上で高い成果を生んでいる理由は、「コンテンツの構造」によって生まれる心理的効果にあります。
-
最後まで見られやすい
ストーリー形式で展開されるため、結末を知りたくなる。視聴完了率が高く、TikTokアルゴリズム上で評価されやすい。 -
保存・シェアされやすい
感情的な共感を呼びやすく、「誰かにも見てほしい」と思わせる力が強い。 -
フォロワー獲得率が高い
世界観やトーンが継続されやすく、シリーズ化すれば「この人の語りが好き」という理由でフォローされやすくなる。 -
商品やブランドと“物語”でつながる
ストーリーの中にブランドやサービスをさりげなく組み込めば、視聴者は「買いたい」ではなく「共感したから興味を持つ」という自然な態度変容が起きやすくなる。
ブランドや企業がこのフォーマットを活用するには?
共感インタビュー演出は、個人だけでなく企業やブランドにも活用可能です。以下に実践的なアプローチを紹介します。
1. 顧客の声をストーリー化する
「ある大学生が、自分に自信を持てたきっかけは、このスキンケア商品でした」
→ 実際のレビューやエピソードを物語形式に再構成することで、宣伝臭のないプロモーションが可能に。
2. 社員・ブランドのストーリーを語る
「この会社に入って、最初に担当した仕事は…」
→ 採用広報や企業ブランディングにも有効。感情に訴えることで“中の人”への共感が生まれる。
3. 社会的テーマと組み合わせて共感軸を広げる
「これは、シングルマザーのリアルな一日」
→ CSR活動や社会的提言を感情の物語として可視化し、ユーザーの「応援したい」を引き出すことができる。
編集・演出面で意識すべきポイント
この演出スタイルで成功するためには、映像編集や構成において以下の点が重要です。
-
映像は“直接的”でなく“気配”を重視(顔よりも手元・後ろ姿・風景など)
-
字幕のフォントは読みやすく、感情のトーンと一致させる(明朝体や手書き風が多用される)
-
BGMは感情に寄り添うローファイ系・ピアノ・ギターなどが人気
-
ナレーションは感情の抑揚がありすぎない“素の声”に近い演出が支持される
編集技術以上に、「どんな気持ちを、誰に向けて語るか」という“設計力”が成功の鍵を握ります。
今後の展開予測:TikTokは「聞くSNS」になるのか?
この共感インタビュー演出の浸透により、TikTokは以下のような方向へ進化していくと予想されます。
-
「ストーリー×感情」を中心としたコンテンツ設計が主流に
-
ブランドが“語りの人格”を持つようになる(ナレーター=ブランドイメージ)
-
TikTok上での“語りかけ型パーソナルブランディング”が拡大
-
オーディオコンテンツとの融合が進む(ポッドキャスト型TikTok?)
つまり、「聞かせる力を持つコンテンツ」が、今後のTikTokにおける支持・拡散の中心になっていく可能性が高いのです。
まとめ:語りで惹きつけ、共感でつながる動画設計へ
TikTokは今、映像よりも“語り”が記憶に残るSNSへと進化しています。
「映え」ではなく「語り」
「演出」ではなく「共感」
「見せる」より「感じさせる」
このシフトを理解し、活かすことが、これからのTikTokマーケティング成功の鍵となります。
あなたのブランドは、どんな“語り”をTikTokで届けますか?
今こそ、ストーリーテリングではなく「語り手としての設計」を始めてみてください。