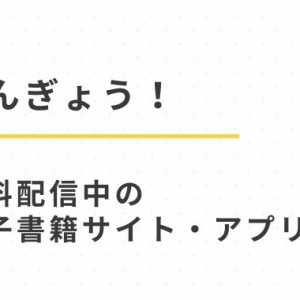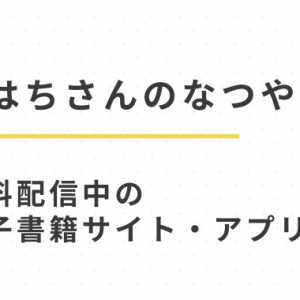TikTokで今、フィクションがバズる理由とは?ドキュメント風ストーリーテリングの可能性
TikTokといえば、リアルな日常や即興性を活かした動画がバズる場として認識されてきました。
しかし2025年に入り、明らかに“作り込まれた物語”――すなわちフィクション性の高いショートストーリー動画が人気を集めている傾向が顕著です。
しかもその多くは、リアルな日常を装った“疑似ドキュメンタリー”型として構成されており、視聴者は「これ本当?」「演技じゃないの?」と戸惑いながらも、思わず最後まで見てしまう構造になっています。
本記事では、TikTokにおけるフィクション×ドキュメント動画の台頭背景と、ブランドや個人がこれをどう活用できるかを掘り下げます。
ストーリーのある動画がバズりやすい今、マーケティングにも「物語の作法」が求められるフェーズに入っています。
そもそも“疑似ドキュメント風TikTok”とは何か?
ここでいう疑似ドキュメント動画とは、以下のような形式を指します。
-
日常を撮っているように見えるが、実は脚本・演出がある
-
出演者の表情・台詞・構成がリアルだが、実際は創作
-
「再現V」「あるある」「もしも設定」などを自然に混ぜている
具体的には次のような動画フォーマットです。
例1:「別れた彼氏に偶然再会した日の記録」
→ 実話風に構成されたドラマ。実際には役者が演じているがコメント欄では“共感”が溢れる。
例2:「新卒営業マン、初契約の瞬間を先輩が隠し撮り」
→ 隠し撮り風・セリフ付き・リアクション重視。企業プロモーションの一環。
例3:「カフェ店員の裏側ルーティン。実は店長が…」
→ ノンナレーションだがストーリー展開がある。エモ寄りの演出。
これらは、視聴者が「これって本当?」と問いながらも感情移入できる設計になっており、TikTokで求められる“親近感”と“物語性”を両立しているのが特徴です。
なぜ今“フィクション×リアル風”動画がTikTokで受けているのか?
TikTokユーザー、特にZ世代・α世代がこのジャンルに惹かれる背景には、以下の要因があります。
-
「リアルっぽいけどドラマ性がある」=ちょうどいい没入感
→ ガチのリアルは重く、完全な創作は嘘っぽい。リアル演出が“ちょうどいい距離感”を作る。 -
感情の起伏が短尺で得られる“物語消費”
→ 数十秒で起承転結があり、観終わった後に“ドラマを見たような満足感”が得られる。 -
コメント欄で「演技上手」「これリアル?」「どこまで本当?」と議論が活性化
→ 視聴者がストーリーの“裏側”を推理し、共感と参加を楽しむ。 -
プロフェッショナル演出への耐性と評価
→ TikTokでもクオリティの高い演出が歓迎され、「ちゃんと作られてる」と評価される空気感がある。
これらの心理背景が、“ドキュメント風フィクション”というスタイルをTikTokの新たな文法として確立させつつあるのです。
成功しているアカウントの共通点と演出構造
このジャンルでフォロワーを伸ばしているアカウントには、いくつかの共通点があります。
【1】ストーリー設計がしっかりしている
-
見始めてすぐに「何の話かわかる」
-
中盤に「転機・対立・驚き」がある
-
最後に「感情の回収・余韻」がある
【2】動画の長さは30秒〜1分が中心
-
短すぎると没入できず、長すぎると離脱率が高まる
-
長編は“前編・後編”などのシリーズ化が効果的
【3】ナレーション・BGM・字幕のバランスが良い
-
テキストだけではなく、音声と映像のタイミングで感情を設計
-
字幕の出る速さ・位置もシナリオ設計の一部
【4】演者の表情やリアクションが自然である
-
プロの俳優よりも“素人っぽさ”を意識した演技が効果的
-
「この人ほんとに体験してる?」と思わせる演出が重要
ブランドや企業が“ストーリー設計型TikTok”を活用する方法
では、こうしたトレンドをマーケティング活動に活用するには、どのような手法が考えられるでしょうか。
1. ストーリーの中心に「価値体験」を置く
ブランドの訴求ポイントを無理に前面に出すのではなく、
-
商品を使うことで変わった人の“変化ストーリー”
-
店舗での「心温まるやりとり」
-
サービス導入によって“助かった”実話風エピソード
など、あくまで人間中心の構成にすることで、押し付け感のない好感的な印象を作ることができます。
2. 「あるある」や「共感」を脚本の柱にする
完全な創作よりも、視聴者が「自分もそうだったかも」と思える体験を基にしたストーリーは拡散されやすいです。
-
「初バイトの日に起きたありえない話」
-
「マッチングアプリで会った人が実は…」
-
「推し活の現場で泣きかけた瞬間」
こうした“実際に起こりそう”なエピソードにブランドを絡めるのがコツです。
3. 社員・顧客を“出演者”として起用
演者に悩む場合は、社員や顧客を起用して「リアルに演じる」ことが可能です。
-
営業マンの実体験を再現する形式
-
顧客のストーリーをナレーション付きで再現
-
店舗スタッフによる寸劇+本音インタビュー
人柄が出やすく、コメント欄での共感も生まれやすい運用方法です。
今後の展開予測とマーケティングへの応用可能性
この“ストーリー設計型ショート動画”は、TikTok内だけでなくYouTube Shorts、Instagram Reels、さらには自社LPや広告バナーにも展開可能です。
特に今後期待されるのは、
-
採用領域への応用(社員のリアルを「演じて見せる」動画)
-
D2Cブランドの“物語訴求”型キャンペーン動画
-
地方自治体や教育機関での「共感型啓発動画」
など、エンタメと教育・広告・広報の垣根を超えた活用が進むことです。
まとめ:TikTokは「物語で心を動かすSNS」に進化している
「動画は短く、内容は濃く」
「リアルだけど、演出されている」
「情報よりも、感情を伝える」
これが、TikTokというプラットフォームの本質になりつつあります。
ただ商品のスペックを紹介するだけでは伝わらない。
ただ雰囲気を見せるだけでは記憶に残らない。
そんな時代に求められるのが、“物語としての設計力”です。
次のアクションとして、ぜひ以下を検討してみてください。
-
自社サービスにまつわる“ストーリーの素”をチーム内で棚卸しする
-
短編脚本(30秒)を書いてみて、社内で読み合わせをしてみる
-
「撮影→編集→演出」のTikTok用ワークフローを整備する
TikTokは今、ストーリーを“映像で語れる人・ブランド”に主役の座を譲り始めています。
あなたのブランドも、「物語のある存在」として記憶に残る投稿を、次の一歩として始めてみませんか?