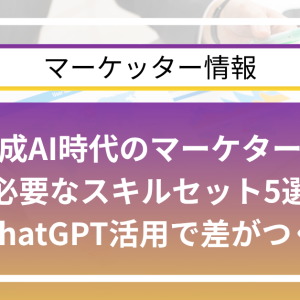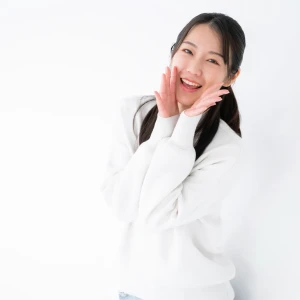TikTokで再燃する「自己診断」系トレンドとマーケティング活用の可能性
TikTokで今、自己診断やパーソナリティ診断系のコンテンツが再び注目を集めています。
「あなたはどのタイプ?」
「恋愛スタイルを診断」
「メンタルの回復速度チェック」
「就活性格分析」など、エンタメと心理学が融合した投稿が2025年春の人気ジャンルとなり、Z世代・α世代を中心に拡散しています。
このトレンドは単なる娯楽にとどまらず、企業やブランドがユーザーの“自己理解”に寄り添いながらコミュニケーションを取るための、新しい入り口としても機能しています。
本記事では、TikTok上で流行する診断コンテンツの背景と構造、実際の人気投稿傾向、そして企業が活用するためのポイントを整理して解説します。
なぜいま「診断」コンテンツがバズっているのか?
診断系コンテンツがTikTokで人気を集める理由には、次のような背景があります。
-
自己理解への関心の高まり(Z世代の“自分探し”文化)
-
SNSに「自分の属性」を共有する文化(タグ・ジャンル付け)
-
フォーマットの簡単さと没入感の両立
-
短時間で参加→結果→共感まで完結する設計
-
視聴者参加型として拡散されやすい構造(コメント欄で盛り上がる)
特にTikTokは、「心理テストを紹介→画面タップで選択→ナレーションや字幕で結果を解説」という流れを15〜30秒で完結させることが可能で、テンポ感の良さが視聴完了率に直結しています。
また、「当たりすぎて怖い」「これはガチで刺さる」といったコメントが自然と投稿を拡散し、フィード上での再生数・保存数も爆発的に伸びる傾向にあります。
注目の「診断系TikTok」フォーマットパターン
診断系のTikTok動画には、いくつかの成功パターンが存在しています。
1. 選択肢スライド式(コメントで回答)
例:
Q. あなたが一番ときめくシチュエーションは?
A. 急な雨のあとで傘を差し出される
B. 仕事で褒められたときに見せる笑顔
C. 相手が真剣な顔で話しかけてくる瞬間
D. 寝る前におやすみのメッセージが届く
この形式では、ユーザーがコメント欄で「C!」などと回答し、そのコメントをもとに次回の動画で解説するという“シリーズ化”が可能になります。
2. 自己分析ツール連携型(外部リンク活用)
「プロフィールのリンクから診断テストができるよ」
「診断結果のタイプ別に、おすすめコーデを紹介」など、
TikTokから外部サービス(診断LPや簡易Webアプリ)へと流入させる導線を設計している投稿も増えています。
Z世代はこのような**“自分のタイプに応じた情報提供”=パーソナライズ**に高い価値を感じており、企業側もCVポイントとしての期待値が高まっています。
3. 音源・テンプレート活用型(流行音源+診断)
診断×音源という形で、「自分に当てはまったらこの音を使って投稿してみて」という形式のコンテンツも拡大中です。
これは診断という行為そのものをUGC化しやすく、ユーザー自身が診断結果を「自分語り」として拡散する仕組みが整っているため、ブランド側のバズ支援素材としても優秀です。
人気ジャンル別:TikTokで流行中の診断テーマ
ここからは、現在特に反応がよい診断ジャンルを紹介します。
【恋愛・人間関係】
-
あなたの恋愛戦闘力診断
-
LINE返信の早さでわかる恋愛タイプ
-
一番距離感がうまく取れる友達タイプ診断
【性格・ライフスタイル】
-
朝型・夜型チェック
-
休みの日の行動からわかるあなたの“本音”
-
ひとり時間の過ごし方でわかるメンタル傾向
【ファッション・美容】
-
肌質タイプ診断(ナチュラル/ツヤ/セミマット)
-
好きな服装からわかる「本当のキャラ」
-
メイクで魅せるべきパーツ診断
【キャリア・自己成長】
-
向いてる働き方診断(1人で集中?みんなで企画?)
-
就活性格タイプテスト(挑戦型/安定型/共感型など)
-
あなたの“武器にすべきスキル”診断
これらの診断は、それぞれ「共感→保存→拡散→会話」というサイクルを生みやすく、特にコメント率と視聴完了率が高い傾向があります。
企業がTikTok診断コンテンツを活用するには?
診断トレンドは、単なるエンタメではなく**企業にとってユーザーとの“接続装置”**になりえます。
以下は、実際に企業が行っている施策と活用法です。
1. ブランド独自の「診断ロジック」を用意する
自社サービスや製品と自然につながるテーマで、独自の診断軸を設計します。
例:
・スキンケアブランド → 肌質診断+おすすめラインナップ誘導
・キャリア支援企業 → 適職診断+求人マッチングへの導線
・ECプラットフォーム → 買い物傾向から見る“タイプ別キャンペーン”設計
ここで重要なのは、診断が“販促目的に見えすぎない”こと。
あくまで「ユーザーの自己理解に寄り添う」という構図を保ちつつ、導線を設計することがポイントです。
2. コメント活用型診断で“シリーズ設計”
診断動画は単発ではなく、コメントから次の動画を生み出す“サイクル化”が理想です。
-
「Bだった人だけに言いたいことあります」
-
「Aタイプの人、こんな時どうしてる?」
-
「Dを選んだ人の“あるある”まとめてみた」
このように、コメント→動画→反応→拡張というループを設計すれば、1投稿から5〜10本のコンテンツに発展可能です。
3. 診断結果ごとの「パーソナライズ動画」でCVに導く
たとえば、3タイプの診断結果があるとしたら:
Aタイプ → 情報整理型 → Notionテンプレの紹介
Bタイプ →行動派 → タスク管理アプリの紹介
Cタイプ →共感型 → 音声メモサービスの紹介
このように、診断結果ごとに「あなたに向いてるのはコレ」と提案することで、TikTok→サービス登録や購入へとつながる流れがつくれます。
注意点と落とし穴:「診断系バズ狙い」に潜むリスク
TikTok診断コンテンツは伸びやすい反面、以下のような注意点も押さえておくべきです。
【1】過度な一般化・ステレオタイプは逆効果
「Aを選ぶ人は恋愛下手」など、断定的・レッテル的な言い回しは炎上の元に。
共感性を重視した柔らかい表現で、ユーザーの“選択を肯定する”視点が重要です。
【2】商品販促が前面に出すぎると離脱率が上がる
診断の面白さを損なうような直接的な販促は逆効果。
診断→自己理解→提案という順序を守ることが、ブランド信頼のカギになります。
【3】外部リンクへの過剰誘導に注意
LPへ飛ばすためだけに設計された診断動画は、TikTokのアルゴリズムに嫌われやすいです。
まずは“その場で楽しめる構造”を徹底しましょう。
まとめ:TikTok診断コンテンツは「共感+提案」の最短ルート
TikTokで人気の診断系動画は、自己理解のニーズに応えつつ、共感と拡散を同時に叶えるフォーマットです。
企業としてこのトレンドに乗るには、「ユーザーが自分を知る手助け」をするという立ち位置が重要です。
次のアクションとしては以下のような取り組みが考えられます。
-
自社商品やサービスと関連する“3タイプ診断”を設計する
-
TikTok用のテンプレ動画構成をCapCutなどで準備
-
コメント欄から次の診断ネタを収集し、投稿をシリーズ化
-
診断結果ごとのCV導線やLPを整備する
TikTokは、商品を“見せる”よりも“あなたに合っている”を伝える場へと進化しています。
その橋渡しとなるのが、「診断型コンテンツ」という新しいトレンド。
今後のブランド戦略に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。