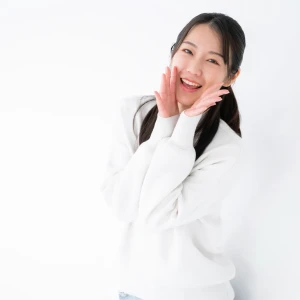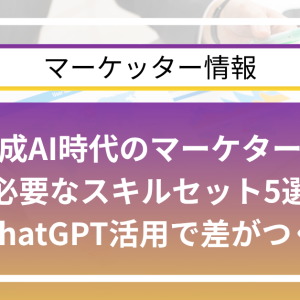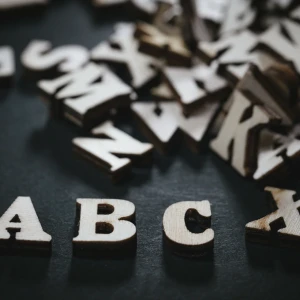TikTokで進化する「コーデ解説」文化とは?Z世代に刺さる“見せ方”の最新トレンド
2025年春、TikTokでは単なるファッション紹介動画ではなく、「コーデ解説」に特化した投稿が若年層を中心に注目を集めています。
これは、ただ着て見せるだけでなく、なぜその組み合わせにしたのか、どこで買ったのか、どうアレンジできるのかを言葉で説明する“語る系”ファッションコンテンツです。
こうした流れは、Z世代が重視する「理由」「ストーリー」「自己表現」の価値観と合致しており、ファッション領域を超えて、コスメ、インテリア、ガジェット、文房具といったあらゆるジャンルに応用されはじめています。
本記事では、TikTokで拡大する「コーデ解説文化」の現状と人気アカウントの分析を行い、企業やブランドがマーケティングに応用する方法について深掘りしていきます。
なぜ「解説すること」がZ世代に刺さるのか?
2020年代初頭、TikTokでは“映える”ビジュアル中心の投稿が主流でした。
しかし現在では、単にスタイルを見せるだけでなく、「なぜそれを選んだのか?」という裏側を語ることが、新たな共感や信頼を呼んでいます。
Z世代が「語り」を好む背景には、次のような価値観の変化があります。
-
消費よりも“選択の背景”を重視する
-
似たような商品が多いからこそ、使い方や意図が知りたい
-
ファッションやライフスタイルを通じて“自分らしさ”を探す
結果として、洋服やコスメといった見た目重視のジャンルにおいても、「言葉で語る」投稿スタイルが支持されているのです。
TikTokで流行中のコーデ解説動画の特徴
コーデ解説系の動画にはいくつかの共通フォーマットがあります。
特に人気の投稿に見られる傾向を以下に紹介します。
1. 声出しナレーションで「その日の気分」や「選んだ理由」を説明
例: 今日は雨だったので白のトップスは避けて、このカーキにしました。
このパンツ、実はウエストがゴムでめっちゃ楽なんです。
バッグは、荷物が多いのでトートに。通勤感が出ないようにキャップ足してます。
このような“友達に話しかけるようなトーン”が特徴で、フォロワーからの信頼や共感を得やすくなっています。
2. ポイントだけ字幕で強調し「ながら見」に対応
-
テキストで補足:「ユニクロ1990円」「汗かいてもサラッと」「洗濯機OK」
-
テロップの一貫性:フォントや配置を統一し、ブランド感を維持
スマホで音声オフ視聴するユーザーが多いため、字幕も丁寧に設計されています。
3. 「失敗コーデ」「昔のダサい自分」との比較
成功例だけでなく、「昔こうだったけど今はこうしてる」と比較する投稿も人気です。
自己変化の過程を見せることで、視聴者は「自分も変われるかも」と前向きな感情を抱きやすくなります。
アパレル以外への波及:あらゆるジャンルが“語り型”に対応
コーデ解説の文脈は、すでに他ジャンルにも波及しています。以下はその応用例です。
【コスメ】
メイクアイテムを「重ねる順番」「質感のバランス」「TPOごとの使い分け」など、解説スタイルで紹介。
例:日中用の艶肌→夜用のマット肌で“朝晩コーデ”として展開
【インテリア】
部屋のレイアウトを「動線」「気分転換」「空間ゾーニング」などの観点で解説。
例:作業スペースの照明を暖色にして“集中しすぎないように”している…といった意図を語る
【ガジェット】
PC周辺機器やスマホグッズの組み合わせに理由を持たせて紹介。
例:このマウスパッド、デスク映えだけでなく“手汗吸収”も兼ねてるんです
【フード/弁当】
お弁当の中身を「飽き防止の色構成」「時短重視」などで解説。
例:赤・黄・緑のバランス+詰めやすさで“朝の3分弁当”
このように、“見せる”だけではなく“理由を語る”ことで、あらゆるジャンルが再解釈されているのが今のTikTokです。
トレンド発信者の共通点:インフルエンサーたちは何を工夫している?
TikTokでコーデ解説ジャンルを牽引しているインフルエンサーには、以下のような共通点があります。
-
自身の「属性」を明確にしている(例:低身長/20代会社員/保育士など)
-
解説する“フォーマット”が定番化している(例:「今日の通勤コーデ3ステップ」)
-
説明しながら“プロすぎない親近感”を保っている
-
コメントを拾って次回の動画テーマに反映している
このように、語り方や構成が固定されていることで、フォロワーは「次も見たい」と思えるループが生まれています。
企業アカウントが「解説型トレンド」に乗るには?
企業としてこのトレンドに参加するには、以下の視点が重要になります。
社員やスタッフが“自分の言葉で語る”ことを許容する
マニュアル化された広報発信ではなく、担当者自身の言葉で「なぜこの商品を推すのか?」を語ることで、リアルな共感が生まれます。
-
なぜこの企画を始めたのか?
-
社内でどんな議論があったのか?
-
自分だったらどう使うか?
こうした人間味のある語りは、TikTokでは高評価されやすい要素です。
カメラに向かって説明せず「手元だけ」や「ナレーション」でもOK
顔出しが難しい場合は、手元+字幕、ナレーション音声だけでの解説でも問題ありません。
実際、人気投稿の多くは「商品+テロップ+BGM+声」だけで構成されており、個人情報や撮影環境のハードルは高くありません。
解説用テンプレートをチーム内で共有する
複数の担当者が投稿する場合、解説テンプレートを用意することでクオリティを保ちながら効率的に運用できます。
例:「冒頭に気候や予定を伝える→トップスの理由→ボトムスの工夫→全体のバランス→結論」
CapCutには解説用テンプレも多数用意されており、非デザイナーでも編集がしやすくなっています。
今後の展望:解説スタイルはブランド戦略にも直結する
「なぜこの商品なのか?」「なぜこの選び方をするのか?」という問いに答える動画は、ブランドとしての思想や価値観を伝えることにもつながります。
-
コミュニティとの共創
-
世界観の浸透
-
顧客の自己実現のサポート
こうしたブランドの根幹部分を、1分前後の短尺で“分かりやすく言語化する”ことが、2025年のTikTok戦略における大きな鍵になるでしょう。
まとめ:TikTokは「語れるブランド」が強くなる時代へ
これからのTikTokトレンドは、ただ映えるだけでは足りません。
重要なのは、「その選び方に、あなたらしさがあるか?」という視点です。
企業アカウントも、ただ機能や価格を伝えるのではなく、「なぜこの企画が生まれたのか?」「この商品をどんな風に使ってほしいのか?」といった意図を語ることで、ユーザーとの信頼関係を築けるようになります。
次のアクションとして、以下を試してみましょう。
-
1本だけでいいので「商品をどう選んだか」を語る投稿を作ってみる
-
社内で「今月の語り企画」をテーマにした投稿会議を開いてみる
-
顧客が“選び方”で迷っているポイントを調査し、説明に落とし込む
語ることで世界観が伝わる。
語ることでファンが育つ。
TikTokの次なるトレンドは、そんな「語り型ブランド」の時代に突入しています。
トレンドを知るだけでなく、トレンドの“中身”を構造化していくことが、今後のマーケティングにおける差別化につながります。
ぜひ自社らしい「語り方」の型をつくってみてください。