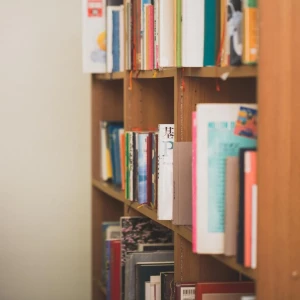TikTokマーケティングで“失敗する企業“の共通点とは?今見直すべき運用設計
TikTok活用を始めたはいいものの、「再生数が伸びない」「社内で運用が回らない」「結局何が成果なのかわからない」と感じていませんか?
実は、これらの悩みは単なる“ノウハウ不足”ではなく、初期設計や意思決定のズレに原因があることが多いのです。
今回は、現場でよく見かける「失敗パターン」を整理しながら、成果につながる運用体制・設計の見直しポイントを解説していきます。
よくある失敗パターンとその背景
成果指標がふわっとしている
「バズらせたい」「認知を広げたい」といった目的は一見魅力的ですが、具体的な数値やゴール設定が曖昧なままスタートしてしまうと、振り返りや改善が難しくなります。
特にBtoB領域では「誰に見せたいか」「どこでアクションしてほしいか」の導線が曖昧なケースが多く、動画単体の面白さばかりを追ってしまいがちです。
“現場任せ”で運用が属人化している
「若いメンバーに任せておけばいいでしょ」というパターンは、短期的にはスピード感が出ますが、投稿に一貫性がなくなりやすく、ブランド認知や信頼形成にはつながりにくくなります。
さらに、属人的な運用は“中の人が抜けた途端に止まる”というリスクも孕んでいます。
投稿が「なんとなく」のアイデアで回っている
アイデア出しをしているようで実は「前回それっぽく再生されたからまた似たような動画を作る」といった属人的な判断基準で回している企業も多いです。
この場合、ネタ切れや内容のマンネリ化が早く、視聴者にも“使い回し感”が伝わりやすくなります。
成果につながる運用設計のポイント
明確なKPIと“次のアクション”を定義する
「フォロワー数」「再生数」「いいね数」などの指標に加えて、その先にある**コンバージョン導線(例:サイト遷移、問い合わせ、採用ページ誘導など)**を明確にしましょう。
それにより「バズるかどうか」ではなく、「戦略的に狙ったユーザーに届けられているか?」という視点で運用を評価できます。
チーム運用に切り替え、“分業型”にする
企画・撮影・編集・投稿・分析という各工程を分担し、「毎週この曜日に振り返りMTG」などのリズムを作ることで、継続的かつ安定した運用が可能になります。
社内にリソースがない場合は、外部パートナーとの連携も一案です。コンテンツ制作をアウトソースし、戦略部分だけ社内に残すというスタイルも増えています。
投稿テーマとシリーズ構成を設計する
投稿ごとに内容をゼロから考えるのではなく、「採用向け」「商品紹介」「社内の日常」など軸となるシリーズを定めることで、運用の負荷を下げながら一貫性を保てます。
また、シリーズ化することでアルゴリズムにも「このアカウントは○○系だ」と認識されやすく、表示の安定化につながることもあります。
まとめ:一歩立ち止まって、設計を見直すことが成功への近道
TikTokの成果は、必ずしも「バズった数」では測れません。大切なのは、誰に何を届け、どんなアクションにつなげたいかを明確にし、それに沿った運用体制を構築することです。
もし今、思うように成果が出ていないのであれば、コンテンツ単体の見直しではなく、運用全体の“設計図”を見直すことが効果的かもしれません。
次のアクションとして、社内で「TikTok運用の目的とKPIを再確認する会議」を開いてみてはいかがでしょうか。現場にいる担当者の声を吸い上げ、再設計につなげる第一歩になるはずです。